Table of Contents
かわいい子猫を探すとき、ペットショップやブリーダーを訪れる人は多いでしょう。でも、そこで売られている子猫たちが、どんな環境で生まれ育ったのか、考えたことはありますか?
環境省の調査で分かった「猫 ブリーダー 数」の実態
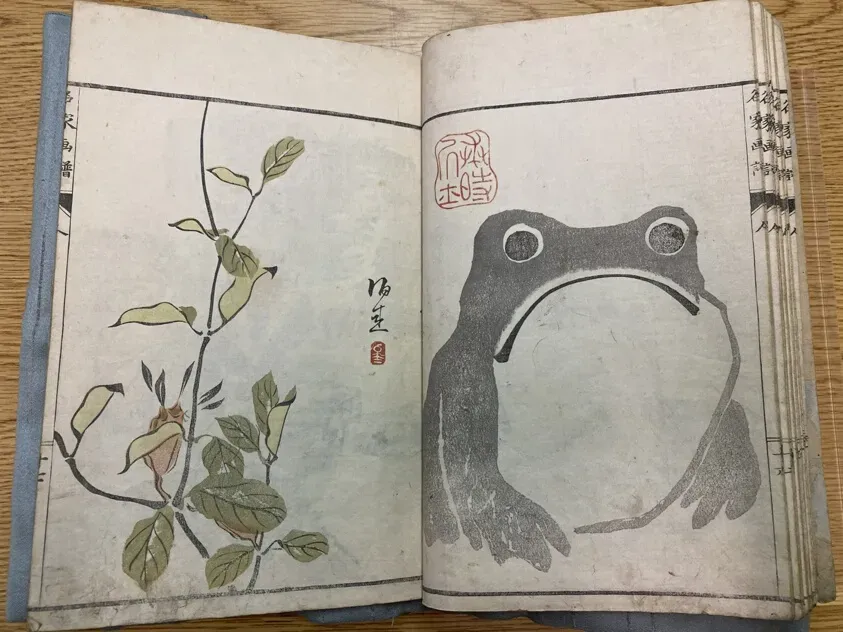
環境省の調査で分かった「猫 ブリーダー 数」の実態
環境省が2023年11月に行った一斉調査、これが結構な騒ぎになったんです。全国のペットオークション業者やブリーダーを対象にしたもので、目的は動物愛護管理法がちゃんと守られているかチェックすること。特に、マイクロチップの情報から「あれ?」と疑わしい動きが見られたところにメスを入れた形ですね。この「環境省の調査で分かった「猫 ブリーダー 数」の実態」は、私たちが想像していたよりもはるかに深刻なものでした。
数字の裏側:偽装される猫の生年月日と違反事例
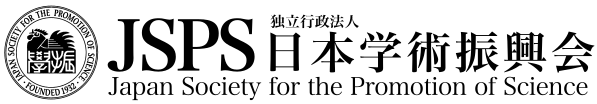
数字の裏側:偽装される猫の生年月日と違反事例
衝撃の数字:約半数のブリーダーで違反
さて、環境省の調査結果、これが本当に衝撃的でした。全国の約1400件のブリーダーを対象にした調査で、なんとその約半数、つまり700件近くで何らかの動物愛護管理法違反が見つかったというんです。
これって尋常じゃない数字ですよね。猫 ブリーダー 数は全国にたくさんあるわけですが、そのうちの半分が法律を守れていない可能性がある、ということです。もちろん、違反の程度は大小あるにしても、これは業界全体として見過ごせない問題です。
特に問題視されたのが、子犬や子猫の生年月日に関する違反。これが全体の違反件数のかなりの割合を占めていました。生年月日の偽装なんて、一体どういうことだと思いますか?
生年月日偽装の手口とその理由
この生年月日偽装、手口はシンプルだけど悪質です。マイクロチップの登録情報で、実際よりも遅い生年月日を届け出るというやり方が確認されています。生まれた日をごまかすわけです。
なぜそんなことをするのか?理由は一つ、規制逃れです。動物愛護管理法では、子犬や子猫は生後56日(一部例外あり)を経過しないと販売や引き渡しができないという規制があります。幼すぎる時期に親から離されると、心身の発達に悪影響があるからです。
でも、早く売りたいブリーダーや業者にとっては、この規制が邪魔になる。だから、生年月日を偽って、実際には月齢が足りない子猫を、あたかも規制をクリアしているかのように見せかけて販売しようとするわけです。これは完全に法律違反です。
違反内容の詳細と動物への影響
生年月日偽装以外にも、様々な違反が確認されています。例えば、飼養施設の面積や構造が基準を満たしていない、従業員の数が足りない、動物の健康状態や取引に関する記録をつけていない、といった基礎的な義務違反です。
中には、病気や怪我をしている子を適切に治療せず放置していた、というケースもあったようです。想像するだけで胸が痛みます。
これらの違反は、直接的に子猫たちの健康や幸福を損ないます。狭い不衛生な場所で、親や兄弟から早すぎる時期に引き離され、適切なケアも受けられない。こんな環境で育った子猫が、心身ともに健康で、新しい飼い主さんの元で幸せに暮らせるでしょうか。
環境省の調査で明らかになった「猫 ブリーダー 数」とそれにまつわる違反の実態は、私たちがペットを迎える際に、その背景にある現実にも目を向ける必要があることを強く示唆しています。
- 生年月日偽装(最も多発)
- 飼養施設基準違反
- 従業員数不足
- 記録義務違反(健康状態、取引など)
- 疾病個体への不適切な対応
なぜ、猫の繁殖現場で問題が多発するのか?
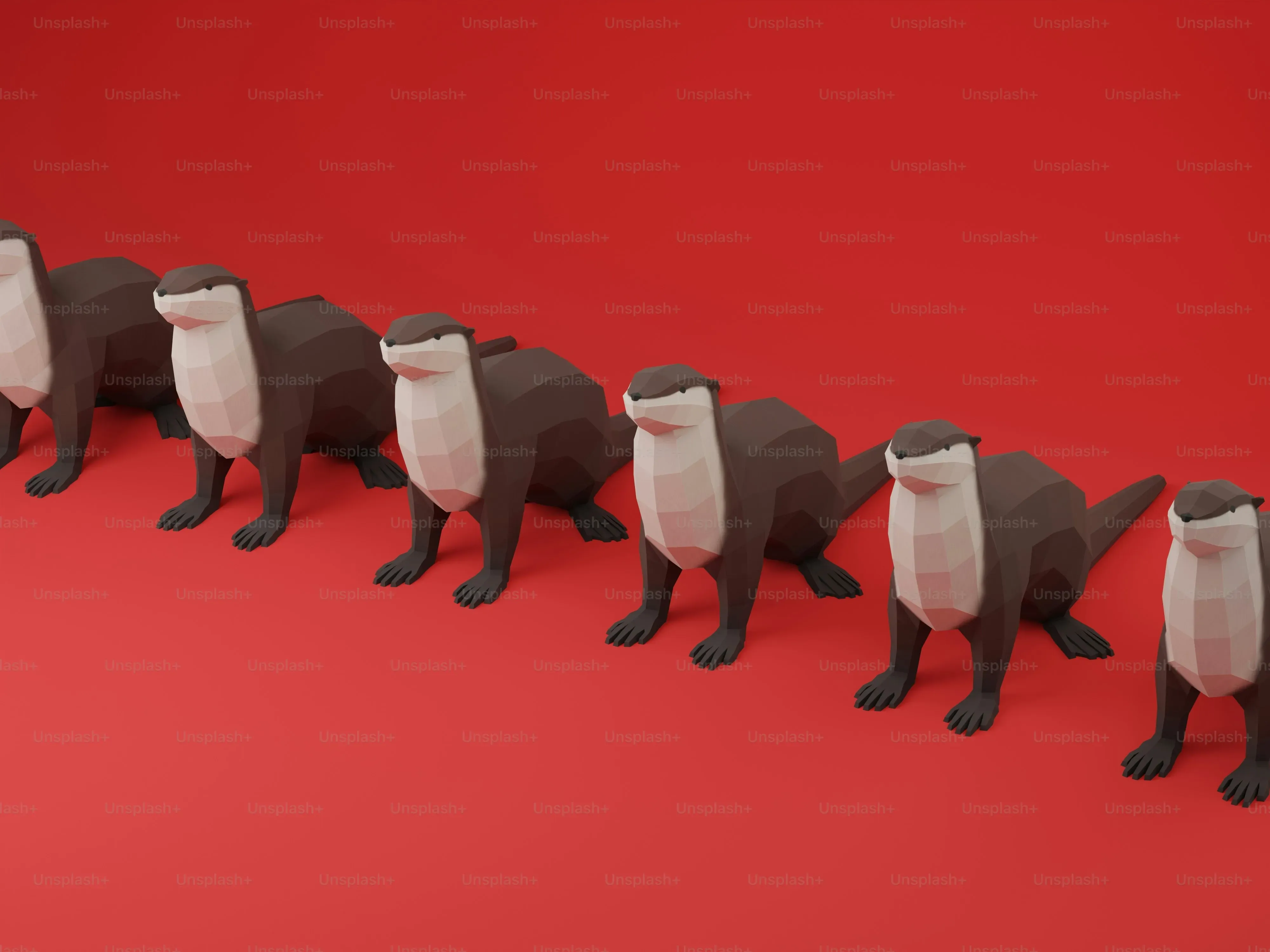
なぜ、猫の繁殖現場で問題が多発するのか?
儲け優先の構造が歪みを生む
正直な話、問題が多発する背景には「お金」が大きく関わっています。猫の繁殖って、きちんとした環境で、親猫の健康管理も徹底して、愛情深く育てるとなると、かなりの手間とコストがかかるんです。
でも、一部の悪質な業者やブリーダーは、そのコストを削ろうとします。狭いケージにたくさんの猫を押し込めたり、必要な医療を受けさせなかったり。そうやってコストを抑えれば、より多くの利益が得られるからです。
特に、まだ規制が緩かった時代からの名残や、知識のないまま始めてしまうケースも。「猫 ブリーダー 数」が増える中で、玉石混交の状態になっていると言えます。儲けを最優先する考え方が、動物福祉を後回しにしてしまう構造的な問題があるんです。
規制と現実のギャップ、そして倫理観の欠如
動物愛護管理法は年々厳しくなっていますが、それでも法の網の目をかいくぐろうとする人たちがいます。生年月日偽装なんてまさにその典型です。法規制があるのに、それを守る意識が低い、あるいは守る気がない人たちが一定数いる。
また、全ての「猫 ブリーダー 数」が専門的な知識や高い倫理観を持っているわけではありません。繁殖に関する正しい知識、遺伝性疾患のリスク、親猫や子猫の社会化の重要性など、学ぶべきことはたくさんあります。
知識や倫理観が欠けていると、無計画な繁殖につながり、結果として劣悪な環境や健康問題を引き起こしてしまう。行政の監視が行き届きにくい点も、問題を助長している要因かもしれません。全てをチェックするのは現実的に難しいですからね。
「猫 ブリーダー 数」を取り巻く問題、飼い主として何ができる?

「猫 ブリーダー 数」を取り巻く問題、飼い主として何ができる?
安易に飛びつかない:信頼できるブリーダーの見分け方
環境省の調査で明らかになった「猫 ブリーダー 数」にまつわる問題、これを知ってしまうと、「じゃあ、どこで猫を迎えたらいいの?」って不安になりますよね。
正直言って、全てのブリーダーが問題があるわけじゃありません。本当に愛情と情熱を持って、猫たちの幸せを第一に考えているブリーダーさんもたくさんいます。問題は、そうじゃない人たちも紛れ込んでいること。
私たち飼い主予備軍ができる最初のステップは、安易に「かわいい!」だけで決めないこと。インターネットで見た情報や、店頭の価格だけで判断するのは危険です。衝動買いは絶対に避けるべき。
まずは、そのブリーダーがどんな人なのか、どんな考えで猫を育てているのかを知ろうとする姿勢が大切です。
見学は必須:自分の目で確かめる勇気を持つ
信頼できるブリーダーかどうかを見分けるには、実際にブリーダーさんの元を訪ねて、猫たちが生活している環境を見せてもらうのが一番です。
「見学お断り」とか、特定の場所でしか会わせてくれないブリーダーは要注意かもしれません。後ろめたいことがある可能性も否定できませんから。
見学に行った際は、猫たちが清潔で安全な環境で過ごしているか、親猫は健康そうか、子猫たちは生き生きとしているか、自分の目でしっかり確認しましょう。そして、ブリーダーさんにたくさん質問を投げかけてみてください。
- 親猫はどんな猫ですか? 性格や健康状態は?
- 子猫はいつ生まれたのですか? (環境省の調査で問題になった点なので特に重要)
- 離乳は済んでいますか? どんなご飯を食べていますか?
- これまでにどんなワクチンを接種しましたか? 健康診断は?
- 遺伝性疾患の検査などは行っていますか?
- 見学に来たのは初めてですか?(猫舎全体を見せてくれるか確認)
- 迎えるまでに気をつけることはありますか?
- 迎えた後の相談にも乗ってもらえますか?
質問に対して、曖昧な答えだったり、説明を嫌がるようなブリーダーは避けた方が無難です。猫への愛情と知識があるブリーダーさんなら、喜んで色々な話をしてくれるはずです。
責任ある選択:倫理的なブリーダーを支援する
残念ながら、環境省の調査結果が示すように、「猫 ブリーダー 数」の中には動物福祉を軽視する業者が存在します。しかし、私たちが責任ある行動をとることで、そうした業者ではなく、倫理的に活動しているブリーダーさんを支援することができます。
少し高くても、遠方でも、時間をかけてでも、信頼できるブリーダーさんから猫を迎えること。それが、劣悪な環境で生まれた子猫たちの数を減らし、業界全体の質を上げていくことにつながります。
また、血統や特定の猫種にこだわらないのであれば、保護猫を迎えるという選択肢も忘れてはいけません。多くの猫たちが新しい家族との出会いを待っています。
私たちが賢い消費者になること、そして猫を迎えることの重みを理解すること。それが、「猫 ブリーダー 数」を取り巻く問題を改善していくための、私たち一人ひとりにできる大切な一歩なのです。
知っておきたい「猫 ブリーダー 数」と、その先の責任
環境省の調査が示した「猫 ブリーダー 数」の裏側は、残念ながら期待通りのクリーンな世界ではありませんでした。多くの現場で法律が守られず、子猫の生年月日すら正確でないケースが横行している現実があります。これは単に一部の悪質な業者の問題ではなく、流通の仕組みや、私たちが「かわいいから」と安易に子猫を迎える姿勢にも関係しているのかもしれません。命を迎えるということは、その子がどこで生まれ、どんな環境で育ったのかを知り、生涯にわたる責任を負うということです。安易な気持ちで迎える前に、一度立ち止まって考えてみること。それが、この調査結果から私たちが学ぶべき一番大切なことでしょう。